�@��������ɂ��Ă��A���܂ǂ��Ȃ��Ă���̂����킩��Ȃ��Ɖ�����ɐi�܂Ȃ��B
������Ɩ����e�̑w�ʁA��ʉ�(���l���j�ƋL�^�̌p�����s���B
������c�a�l�i�f�[�^�[�x�[�X�}�l�[�W�����g�j�Ƃ��Ĉ�̌o�c��@�ɂ܂ō��߂��̂��O�ɂ����n�ƎВ���
�����ł���B��Ɣ閧�Ȃ̂ŏڍׂ͘b���Ȃ����A�o�c�̍��i���Ȃ��d�v�ȍl�������ƍ��ł��v���Ă���B
���̌�A�c�a�̔�r�A�����L���O���s���B�m�n�P�̎d���̎d����͕킷�邾���œ������ʂ����W�J�ł���B
�F��������ɋ�J�������B�ł��A�������疔���P���i�ނ̂ł���B
�@
�悸���܂��Ȃ��̌��t���Љ�܂��傤�E�E�E
�@�@�@�@�@�@�@�@�u�_���͎��A�m���ɐ�����A�ߐH�Z�v
������o���Ă����A�Ȃ�ƂP�U��̉�b�̂˂��ŁA�R�~���j�P�[�g�ł���B
�i�P�j�@���E�E�E�Ƒ��̘b
�i�Q�j�@���E�E�E�C��̘b
�i�R�j�@�ˁE�E�E�肢�i���j�̘b
�i�S�j�@�́E�E�E�͂��(���s)�̘b
�i�T�j�@�ƁE�E�E�F�B�̘b
�i�U�j�@��E�E�E���W���[(��y)�̘b
�i�V�j�@���E�E�E���i���s�j�̘b
�i�W�j�@���E�E�E�o�g�n�̘b
�i�X�j�@���E�E�E�́i���N�j�̘b
�i�P�O�j�ɁE�E�E�j���[�X�̘b
�i�P�P�j���E�E�E�ِ��i�����Ⴕ���͒j���j�̘b�j
�i�P�Q�j���E�E�E����̘b
�i�P�R�j��E�E�E�~�]�̘b
�i�P�S�j�߁E�E�E�����̘b
�i�P�T�j�H�E�E�E�H�ו��̘b
�i�P�U�j�Z�E�E�E�Z�܂��̘b
�@�Ƃ��������ɂȂ�L�[���h����ӂŊo������B�A���A�����ꂪ�o�Ă���̂ł����ӂ��I�@
����́A����L���Ȍo�c�҂̌��t�ł����A���̌��t����O�����ȃv���X�v�l�������鎄�̍D���Ȍ��t�ł���B�����āu���]�є��N���v�܂��������̌��t�ɂ́A�s���s���̐l�Ԃ̖ړI�B���ӗ~���`����Ă���B
�@
���������Z���^�[�̏����Ƃ��ē��k�̒n�ɂ������̎��́A���܂ł��Y����Ȃ��B�l��5���l���̒��ł��������A�����ɂ�NEC��x�m�ʃ[�l�����ƌ��������������Ƃ��������i�o���Ă����B�H�ƒc�n�̈�p�Ɉʒu����䂪�����Z���^�[�͍H��ƕ��݂���Ă��Ė�X�O�O�O�ؕ����̒��^�Z���^�[�������B�@���́A�Ǘ��E�̓����Ă���}���V�����ɓ��ꂸ�A�P�g�A�w����P�O���̃A�p�[�g�̂QF�ɋ����\�����B�O�C�����Ƃ̈��p���́A�����ς�W��ւ̈��A����ł������B�@�w�ǂ��c�Ə��ւ̊�݂����A�����S�������B�O�C�����́A�ǂ��炩�ƌ����Ɠ��ٌc�̊O�˂��݂̃^�C�v�ŁA�O���ɂ���ڂ������Ă����B���́A�ǂ��炩�ƌ����Ɠ����̐��̊�ՂÂ��肪�����̎g���ƍl���Ă����B�@�������������̃Z���^�[�͔z���s��i��z�A��o�ׁA�������X�j�����Q�O�O�����x�����ĔߎS�ȏł������B�����炱�������������ɕ��C�������R���������B
�@���́A��\�ɂȂ��Ă���^�o�R���z���悤�ɂȂ����B
������Ȏ��͐l�Ƃ̉�b�́h�ԁh������悤�ɂ���ׁA�^�o�R���z�����Ƃ��o�����B
�������S�S�̎��A��ЂŌ���ꂽ�ꏊ�ł����i���o���Ȃ��Ȃ����̂ł���B(�����V�X�e����)�����Ă��鎖�ɋC�Â����B�����A�^�o�R�̓z��ɂȂ��Ă��鎖���E�E�E�^�o�R���z�������Ǝv���ƁA�Z�������ł��i�����ɍs���^�o�R���z�킸�ɂ́A�����Ȃ��I�@���ŁA�����̓^�o�R�̂����Ȃ�ɂȂ�̂��낤���Ɛ^���ɔY�B
�@�����Ă��̎��A���͗L�镨���~���������B�����m�[�g�p�\�R���ł���B
���̓����A����T�O�{�̃^�o�R���z���Ă����̂ŁA���������U�O�O�~�g���Ă����B
�l���Ă݂�ƌ��ɂP�W�O�O�O�~���^�o�R���z���Ă����̂ł���B�^�o�R���~�߂�A�p�\�R�������[���Ŋy�ɔ������Ƃ��o���邵�^�o�R�̓z�ꂩ����J�������ƍl���A�։������ӂ����B������3�����A1�N�Ǝ����o�ɂ�ă^�o�R�����S�Ɏ~�߂鎖���ł����B�������A24�N�Ԃ��^�o�R���z���Ă����ƌ������́A���ꂾ���łT�O�O���~���z���Ă������ɂȂ�B
�։����Ă݂�Ɣ@���ɖ��ʂȋ����g���Ă��������킩�����B
�@�։����č��A�V�N�߂������^�o�R���z��Ȃ��l�����ɖ��f�������Ă����ƁA���͔��Ȃ��Ă���B
�@
�@
�@���̓����쐬�����Ɩ��v���O�����́A�T�O�{�ʂ������ƋL�����Ă��邪���͂����Ȃ��B
�Ƃ���ŏo���̗ǂ�������۸��ѿ�������͉�Ђ̎В��ɂ�������A���̊Ԃɂ�
�p�b�P�[�W�\�t�g�����̔����������ł��B�ׂ������������ǂ����͒肩�ł͗L��܂��E�E�E�E
���쌠�Ȃ�Ă��̂��������̍������i���]�����ꂽ�����ƂĂ������������B
�@���̃\�t�g���́A�u�������ޔ����V�X�e���v�ƌĂ�ł�������ǁE�E�E�E
�����̋@��ʐ��Y�v�搔����͂���Ɛ��i�ɕK�v�Ȏ��ސ��ʂ��Z�o���A�����K���ɂ���
�ƎҒP�ʂɒ������s����Ƃ������D����̂ł������B
�@�悭�d���̒��Ŏg���u���v���Ă������������낤���H�@
�d�����s����ł̖��Ƃ́A�ȉ��̂悤�ɒ�`�����痝�������₷���B
�@�@�i�P�j���Ƃ́A�ڕW�ƌ���̃M���b�v�ł���(������������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ł���j
�@�@�i�Q�j���ЂƂ̒��ɁA���_�͕������݂���B
�@�@�i�R�j���Ƃ́A��̑łĂ錴���ł���B
������`����ƁA�悭�g���Ă�����Ƃ͈Ⴄ���Ƃ��킩��B
�@�@��j�u�J���~�邩�A�U��Ȃ������ꂪ���ł���v����͖��ł͂Ȃ��I
�l�̗͂œV����R���g���[���ł���Ȃ���ƂȂ邪�E�E�E
�@�A���A�J�ɔG��Ȃ��ʼnƂɋA��Ȃ���ƂȂ�B�P�������A���C���R�[�g�𒅂�A�ԂŋA�铙�X�B
���Ⴆ�A�ȉ��̎����Ԏ��̂��l���Ă݂܂��傤�B
�@�J�̍~��ӁA�Ƌ��旧�Ă�A�N���A��t�������A��ɓ��H�ɂ����Ă������Ƀ^�C��������
�@�d���ɎԂ��Ԃ����B
���̎���̖��́A�d���ɎԂ��Ԃ������ł���B
�@���Ⴀ���̂̌����͉����ƌ����ƈȉ��̂S�̖��_���グ����B
�@�@�@�@�J���~���Ă��ĘH�ʂ�����₷���������ƁB
�@�@�@�A�Ƌ��旧�ĂŁA�Z�\�����n���������ƁB
�@�@�@�B���C�тщ^�]�������ƁB
�@�@�@�C���H�Ɍ��������Ă������ƁB
�@�@�@�ȏ�S�̖��_�����������A��L�̂����@�͎�̑łĂȂ������ł���̂Ŗ��_��
�@�@�@�Ȃ�Ȃ��B���̇A�`�C�͎�̑łĂ鎖�ł���̂Ŗ��_�ƂȂ�B

�@���̓��Г����́A�܂��Z�Ղ��x������Ă������A���̌シ���ɓd�삪���y���������B
�����Ƃɓ��Ђ������́A�����I�������̍ɋ��z���v�Z������ꂽ�B
�d����g���Čv�Z����̂����A���Ղ��P�{�̎w�őł��Ă����̂Ŏ��Ԃ�������A����
�����ŏI���̒I�����́A�ߑO�l�ł������B
�@�����ň�O���N���ēd��𑁂��łĂ�悤�ɌP�����鎖�ɂ����B
���K���@�́A�����ĊȒP�ł���B�L�[�{�[�h�������ɂP����P�O�O���̑����Z�����Ă��������ł���B
�ԈႦ����A�ŏ����牽�x����蒼���B�P�{�Q�{�E�E�E�P�O�O���������������o��܂ł�葱����B
���A��2�T�ԂŁA����܂ŌߑO�l�������I����������ƂQ�P���ɏI���悤�ɂȂ����B
�ł��܂��ۑ肪�������B�E��Ńu���C���h�^�b�`���}�X�^�[�����̂͗ǂ��̂����A�v�Z���ʂ��L��
����̂ɉ��M�����̓s�x���K�v���������̂ł���B�����ő�w����Ɋw����o�ς̖@����
���p���A������g���ē����ɍs���悤�ɍH�v���Ă݂��B�E��ɃG���s�c�������A����œd���������
����ɂ��A��ƏI�����Ԃ́A�X�ɂP���ԒZ�k�ł����̂����E�E�E�E
�@�������c�O�Ȃ��玩���Ɏ���ẮA�P�Ɏc�Ƒオ�����������̌��ʂɂȂ����B
�����C�ɂȂ鎖����A�d�����x���z���c�Ƒ����āA�d���̑����l���ӂ��҂Ɖ]����̂�
�ǂ������������Ǝv���B�ŋ߃z���C�g�J���[�G�O�[���u�V�������b��ɂȂ��Ă��邪�A����������̎d����
�����A�������]�����Ȃ��Ǘ��E�������Ȃ�Ԉ�������ʂɂȂ�Ǝv���͎̂��������ȁH
�@
�y�b�x��z
���z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�����Ƃ́A�z���C�g�J���[��J�����ԋK���̓K�p���O�Ƃ��鐧�x�B
�@�]�v�Ȏ������A�z���C�g�J���[�Ƃ́A�f�X�N���[�N��c�ƃ}���Ƃ������������C�V���c�𒅂Ďd����
�@����l�B�̎����u���[�J���[�Ƃ́A�������̒��ڍ�Ƃ��s���l�B�̎��������B




�@���������Z���^�[�����Ƃ��ď��߂Č���ӔC�҂ɂȂ������̎��ł���B
���S�q���Ǘ��E�ē҂͕K�C�炵�������I�ɊO�����C�ɍs������ꂽ�B
����́A�����ȉ�Ђ̊Ǘ��E���W�܂��Ă̍����u�K�ł������B
�@�����R�l�ƎQ�������u�K�ł͂��������A�����͍u�t������I�ɘb�����ďI������B
�Q���҂̂قƂ�ǂ����Q�̎��ԂɂȂ��Ă����B
�@�������Q���ڂ̍u�t�́A�x�e�����炵���Q�����Ȃ��ׂ̃e�N�j�b�N����g���Ă����B
�u�`�̒��ŁA�r�f�I����������A�u�K�҂Ɏ����������ƐQ�Ă͂����Ȃ��E�E�E
�����ċɂ߂��́A�ǂ���点���B���R�A������Ђ̃����o�[�͂��ɂ��ꂽ���B
�@�悸�́A�ǂ̒��ł��ꂼ��������S�����߂邱�ƂɂȂ����B
���\�҂����͒N������肽����Ȃ������̂ŁA���͗��悵�Ď���グ���B
���̔ǂɓ�������Ђ̓������A�ǂ̃����o�[�̒��Ԃ���������Ă���B
�@�ǂ����A�N���Ȃɂ����Ȃ��l�������W�܂����悤���B
���̕��́A�}�C�y�[�X�ŋc���i�s�A���L�A���\�܂őS�Ă�����Ŕǂ̊F�������������B
���A�ŁA�`�[�����[�N�悭���\�ł������A���̔ǂ͂Ђǂ������I
�@�����ĉ�Ђ̓����R�l�����̉�Ђ̊Ǘ��E������ł������B
�����Ėʔ������Ƃ��C���t�����B�������W�̊Ǘ��E����ԏo�����������ɁE�E�E�E
����ϐg�̕ېg���D�悷��̂��낤�B������낤�Ƃ͂��Ȃ��B
���S�q���́A�S�Ă̋Ɩ��ɗD�悷��d�v�����Ȃ̂ɁA��l�͂킩���Ă��Ȃ�
�����̐g����ԉ����̂ł��낤�E�E
�@����́A���������Ƃ��ď����������������̍w���Ɩ��ŁA�N���������s�k�ł���B
���̓����A�S�����Ă������i�̒��ɃI�[�������i��E�T�b�V���������B
�I�[�������i�ł����ނ͍ɂ�p�ӂ��Ă���A����[�i�܂łP�T�ԂőΉ����Ă����B
�����玑�ސ�́A������Ȃ����ł��������B
�@���i�̔��v�悩�琻�i�̕��i�W�J���s���A�̔��̏�Ԃ���l�����ēK���ɂ�����
�����ʂ����߂�̂ł��邪�A�I�[�������i�����Ɏv��ʗ��Ƃ����������ɂ͂������B
�����ʂ�A���ނ̕��i�E���o���\��COPY���Ĉ�A�̍�Ƃ��s���A���������쐬����
�Ɩ��͖����I������̂����A���͑ؗ��ɂ̊��啝�ɒ������ɂɂȂ�������
���o�����B
�@�@�@�u����Ă������I�v����ꐺ�ł������B
���̐��i�͍ŏ��ɘb�����ʂ�I�[�������i�ł������V�t���^�C�v�̎��قƂ�ǂȂ��B
��������ʃT�b�V�Ȃ璆�V�t���嗬�Ȃ̂ł����B
�@�������i�E���o���\�������������A�ԈႦ�Ē��V�t�p���g���Čv�Z���Ă����̂ł����B
���ǁA��i�̌W���Ɏ����̎��s������̂ł����A�Ȃ�Ƃ��̏�i���������s���ߋ���
���Ă����̂ł����B�W���́A���Ă����܂����u�͂͂́A���O����������I�v�ƁE�E�E
���ꂩ��A�ؗ��ɏ����g�\�ASCR�ƎҎ�z�A��������ƐӔC������Ď�������n����
�S�čs���܂����B���������A���V�t�̕��i�E���o�����\�����̎��ꏏ�ɔp�����܂������E�E�E
�@
���A�C�f�B�A�ɋl�܂������ɂ́A�I�Y�{�[���̃`�F�b�N���X�g�����ɗ��Ǝv���̂Ōf�ڂ��܂��ˁB

����́A���ς��Ď����ŕ��������l����(VA)�̘b�����܂��B
�ȉ��ɂ��̌����Ƌ�̓I�ȍl�������q�ׂ܂��B
�P�T�N���O�ɕ��������Ȃ̂ŁA���X�K�t���Ă��邩������܂��E�E�E
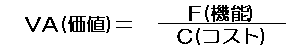
�i�P�jVA�̊�{����
�@�@�@���_�̏���
�@�@�A�W����
�@�@�B���
�i�Q�j�T�̎v�l���[�g(��F�l�p���i�b�g�ŌŒ肵�Ă���)
�@�@�@�Ώۏ��i�͉����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�l�p�i�b�g
�@�@�A���̓����͉����@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�Œ肷��
�@�@�B���̃R�X�g�͂����炩�@�@�@�@�@�@ �F�Q�O�~/��
�@�@�C���ɂ��̓������ł��Ȃ����@�@ �F�Z�p�i�b�g(�W���i)
�@�@�D������̃R�X�g�͂����炩�@�@ �F�P�Q�~/��
*���������킩��A���߂����̉����͂������������ł��B
�i�R�j�P�Q�̒��
�@�@�@�r���E�E�E�E�E�E�E�E�E�������߂���
�@�@�A�����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E����ɂ�����
�@�@�B����Ɨ�O�E�E�E�E����͉����N�����
�@�@�C�萔�ƕϐ��E�E�E�E�E�ς����̂�������������
�@�@�D�g��Ək���E�E�E�E�E�傫�������珬����������
�@�@�E�����ƕ����E�E�E�E�E��������������番������
�@�@�F�W��ƕ��U�E�E�E�E�E�܂Ƃ߂Ă݂��番�����Ă݂���
�@�@�G�t���ƕ����E�E�E�E�E�t����������A�������ɂ킯����
�@�@�H�����̓��ւ��E�E�E�g�ݗ��Ē�������
�@�@�I���ʂƍ��فE�E�E�E�E������_��������
�@�@�J�[���Ƒ�ցE�E�E�E�E���̂��̂��g������ւ�����
�@�@�K����ƒ���E�E�E�E�E�����ɂ������A�����ɂ������
�悤�̓K���c�C�e���̂���Ă鎖���w��ɂ���Ə�L�̂悤�ɂȂ�̂��ȁE�E�E�͂͂�
�@�������ł������̐l�O�Řb���������̂́A���͍��Z�̎��ł����B��������Z�Q�N�ŃN���u�̃u���X�o���h�����ɂȂ��Ē����̎��ł����B����́A�V�����ւ̃N���u�Љ���s�����ł����B�@����܂Ŏ��́A���C�Ől�O�Œ���̂���̋��ł����B����͍��ł������ł����E�E�E�܂��Ă�V����300�l�̑O�łȂǁA�ƂĂ��l�����Ȃ����Ƃł����B
�������N���u�̕������������ȏ�A�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����ł����B�{���͓������������̂ł����E�E
�@���\�����܂ŁA�オ���Ē���Ȃ��Ȃ�����ǂ����悤�ƃN���N���Ɖ������l���Ă��܂����B
�����P�O���Ԃ̏Љ�Ԃ������Ԃɂ��������܂������I����Ă݂�ǂ��ƌ������Ƃ��Ȃ������ł��B
���������́A�o���Ă���܂���ł������E�E�E���ꂩ��́A�������P�O���̔��\�ׂ̈ɁA�����Ԃ��Y�ݍl���邱�Ƃ̓o�J�o�J�����Ǝv���悤�Ȃ�܂����B���ꂩ�玞�͗����Ђ̒��ł����Ɩ��̂��|�X�g�ɕt���܂����B
�l�O�Řb�����ɂ���R�Ȃ��ł���悤�ɂȂ�܂������A������������̎�o�Ƃ��ďj�����q�ׂ鎖��
�Ȃ�܂����B�@�d���̘b�Ȃ�ǂ����Ă��ƂȂ��̂ł����A�t�H�[�}���Ȏ��ł̘b�͐��܂�ď��߂Ă̌o���Ő���
���A�Y��ł��܂��܂����B
����́A���ɃZ���^�[���̖��ɒp���Ȃ��悤�ɂƉ]���v���b�V���[���L��܂����B
�����ŁA�����̎w�j���R���߂܂����B
�@�u��́A���e��ǂ܂Ȃ��ŁA���A�����邱�ƁB
�@�@��́A���X��������Ȃ��łR���ȓ��ŏI��炷���ƁB
�@�@��́A��Ђ̐�`�����{�l�̎d���Ԃ���Љ�邱�ƁB�v
�@�ȏ�̎O���s���ׂɁA�j���̌��e�����܂����B
�����l�O�ŏオ��͖̂h���Ȃ��̂ŁA�e�Ɋp�A�ŏ��ƏI���̌��t�́A��^���A�����p���ĊۈËL��
���x�����\�P�����s���܂����B���A�ŁA�����ɖY��邱�Ƃ��o���܂���B
�@�@�@�@�u�������Љ�ɗa����܂���������Ђ́����Ō�����܂��B�V�Y�A�V�w���тɂ����Ƃ̊F�l���A
�@�@�@�{���́A�܂��Ƃɂ��߂łƂ��������܂��B���ĐV�Y�́����N�́A�E�E�E�E�E�E
�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�@�@�V�Y�A�V�w�̖��i���K�������F��v���܂��Ė{���̎��̈��A�Ƃ����Ē����܂��B�{���͂ق�Ƃ���
�@�@���߂łƂ�������܂��B�v�����l�ŁA�Z���^�[���߂��U�N�ԂłP�P�g�̌������̏j���⊣�t�̈��A���s�������ł��܂����B�i�������Ƃ͎v���܂����A�����̈��A����Ԃ悩�����Ƃ��������Ē����܂������ǁE�E�j
�@�m����1�ГƐ�̐��ɂ���Ƌ��������������Ȃ��Ȃ�}�C�i�X�v�f���L��Ǝv�����A���͑̐��ɂ�郁���b�g�̕����ŏI�I�ɂ͑����ƍl�����B���ہA���܂ł͏o�חʂ����Ȃ����ł��e�ЍŒ�1��̔z�Ԃ����Ă����̂���1��̎ԂŁA�Q�Е��̉ו������������Ƃɂ���ĕK�v�Œ���̎Ԃʼn^�p�ł���悤�ɂȂ����B�A���A������o�חʂ̐�X�̌��ʂ������Ă̑̐��ł��鎖��F�����Ȃ��ƁA���グ���㏸�ɓ]�������ɂ͋t�ɑΉ������Ȃ����邱�Ƃ��̂ɖ����Ȃ�������Ȃ��B���\��Ȃǂ��̐��ɂ͂Ȃ��A���ω��ɉ������̐������邩�ۂ��ɂ������Ă���B
�@�����̕����Z���^�[�́A�g�D���c(����)�ł������B�Ј��A�\�����͉�Ђ�3�ЁA�^����ЂP�O�Ђ̍����ł������B��肪����ΐl�̂����ɂ���悤�ȐӔC�����̑̎��ł������B�������C�����̂́A�o�u�����͂�����1991�N�ł������̂ŁA������C�Ƀ��X�g����f�s�����B�^����Ђƍ\���O����v���Ă����ő��I�Ђ́A�^�c�̊j�������̂ŁA�o�u�������ɓ������O������̌_�����@�ɊO��Ē������B�ŏI�I�ɁAI�ЂƎЈ��̑̐��ɂȂ����̂͒��C����1�N����v�����B

�@�c�ƍ팸�Ɏ��g���Ɋw������Љ�܂��傤�I
���̎���́A�{�l�̖��ł͂Ȃ��d�����w��������i�̖��Ŏc�ƂɂȂ��Ă����Ɖ]�����e����
�P�[�X�ł����A�̐S�̏�i�́A�]���ċ��Ȃ������ƌ����I�`�����܂��E�E�E
�L�鏗�q�Ј�����������ȓ������Q���Ԏc�ƂƂȂ��Ă����̂Œ��ׂ����̎��ł��B
�@�ŏ��ɂ��̓��̋Ɩ���{�l���畷���܂����B����Ƃ��̓��́A����1�x�A�ے��̎d����
�����Ă��āA���ꂪ�c�Ƃ̌��������������킩��܂����B
���̋Ɩ����e�́A�V�ݏZ��H�ː���S���ƌ��ʂɕ\�ɂ܂Ƃ߃O���t�ɏ������ޓ��e�ł����B
�쐬�����O���t���t�@�C�����O���ċƖ��͊����ƂȂ�̂ł����A�C�ɂȂ鎖���������̂ň��
�����܂����B���̃O���t�͒N������̂ƌ����ƁA�O�̉ے�����w�����ꂽ�Ɩ��Ȃ̂ō��́A̧��
���Ă��邾�����Ƃ킩��܂����B
�@�]�����O�C�̉ے����w�����Ă��������A���̂܂܌p�����čs���Ă����̂ł��B
�V�C�̉ے��ɂ��̎����]���ƁA�ǂ���瑼�����ł������Ɩ������Ă��āA��������f�[�^������
�v��̂��Ƃ킩��܂����B
�@�����Ĕޏ��̎d���́A�����s�v�������̂ł��B
�����A�ޏ��ɗ������炻�̎d�����~�߂�悤�ɓ`���܂����B
�����ŋC�����Ȃ�������Ȃ����P�������܂������Ɏd���𗊂���~�߂�Ɖ]��Ȃ���
�@���܂ł������Ă������ł��B�j�Ȃ�N�����Ȃ��������쐬���܂��A�����͎w�����ꂽ�Ɩ���
�~�߂�Ɖ]��Ȃ��Ǝ~�߂Ȃ��̂ł��B
�@������d���̒I�������ʂ���i�͕�������z���グ�v��Ȃ��d�����~�߂����Ȃ�������܂���B
�����ɁA�u�m�[�c�ƃf�[�ł��B�H�v���Ďc�Ƃ����炵�܂��傤�v�Ɖ]����Ђ��L��悤�ł����A�K�v��
���́A��i�������̂���Ă��鎖���A�������茩�Ă����鎖�ł��ˁB
�@
�@������A��y�̋Z�𓐂�����Љ�����B
���̏ꍇ���̂Ȃ�ł̘͂b�ł͂��邪�`�g������@�������E�E�E�E
�@�����������ɉk�ꂸ��Ђɓ����Ă���ŏ��̎d�����d�b�Ԃł������B
�悸����̖��O���悭�킩��Ȃ����A�܂��Ă�����̐l���킩��Ȃ��B
��y�B�́A��p�ɓd�b���Ă��ς��Ə������Ă���B
�@���Ƃ�����d�b���ő吺���グ�āA�������������߂���ł������B
�@�����ł���ӁA��v���Â炵�Đ�y�B���A������A��y�̊��̒����������Ă݂��B
�_���ʂ�A���镨�������鎖���ł����B
�@�����ɂ́A�N������S�����Ă��邩�̃��X�g���������B���A���͉�ЁA���Ӑ�̏Z���^��
�������B�����A�Ă����i�̺̂�߰�́A�����Ő����ꂽ�̂ł����Ă�Ă����j
�@�����Ď�����́A�d�b�̉����X���[�Y�ɏo����悤�ɂȂ����B
�����́A���è�Ŋ��Ɍ����|�����Ă���̂ł��̋Z�͂ł��Ȃ����E�E�E
�@�̂̐E�l�́A�t���̋Z�𓐂�ŋZ�\��g�ɂ����Ƃ����܂����A����͉����E�l������
�b�ł͂Ȃ��A�r�W�l�X�̐��E�ł��������Ǝv���܂��B
�@�������ɗ��X���̐��Y�v����쐬���H��ɂe�`�w����Ɩ�������܂���(�S���͂P�O�l�j
�����Ɏ��т��v�����^�[����o�͂���A���i�S�������Ƃ��̒��[��D�������A��Ƃ��s��
�̂ł����A�]�L�`�K���ɐݒ�`���Y�K�v���Z�o���A��Q�O�O�i����x�L��̂ŁA�����I��
����̂́A�[��ɋy�т܂����B�������A��y�̂t�������A�����莞�ŋA���Ă��܂����B
��̂ǂ�ȃg���b�N���L��̂��A���͂t����̎d���ɂƂĂ��������N�������A�ώ@���Ă݂܂����B
�ώ@���Ă݂āu���A�Ȃ�قǁA�����������̂��I�v�ƂĂ����������������ł��v���o���܂��B
�@�����͂������ĒP���Ȏ��ł����B�t����́A�����ɂłȂ��Q�T���ɒ��߁A���̎��_����
���Y�v����쐬���Ă����̂ł����B�����t����́A�F�Ǝ�����Ƃ����ėI�X�ƍɒ��[��N�����
����܂��ꂸ�Ɏg���Ă����̂ł����B



�@�������Ȃ���A�܂��I�������̍쐬���莞�ŏI���Ȃ��̂ŁA�X�Ɏ��Ȃ钧����s�����B
��ЂɃp�\�R���̍w����\�����ꂽ�̂ł���B�c�O�Ȃ���A���̓����͂܂��Ɩ��p�̃R���s���[�^��
��p�̃I�t�R�����嗬�̎��ゾ�����̂Łu�p�\�R���Ȃǂ����Ă̑��I�v�Ɖ]�����ň�R���ꂽ�B
�@�ł�������Ŏ҂ł���B��x�v�����ƍŌ�܂ł��Ȃ��ƋC�����܂Ȃ��B
�����A�������P�O���~�̎���ɒ�����S���͂����ċ����̂T�{������p�\�R�����w�������B
���������̃p�\�R���́A�܂��d�������Ă���ʂ̃J�[�\�����_�ł��邾���̂�����̂������B
�v���O���������Ȃ��Ǝd�������Ȃ��̂ł���B�����ă}�V�����\�͂WBit�ōő���ذ���U�S�j�a�̂�����̂������̍Ő�[�������B
�@
�@�������͗ǂ��������̂́A�v���O��������̕������Ȃ���Ȃ�����B
�����Ƃ�A���H�h�̐l�ԂȂ̂ŋ��ȏ��I�}�j���A�����ꂩ�������C�́A�����Ƃ��Ȃ������B
�ł͂ǂ������̂��Ɖ]���ƁA���p�a�`�r�h�b�v���O�����W���Đ悸���̃v���O�������߿�݂ɑł����B
�����āA�v���O�����𑖂点�ĈӖ��𗝉�����悤�ɂ��Ă������B
�@�ł�����Ă݂���v���O�����̊�{�́A�ӊO�ƊȒP�������Binput(����)-process(����)-output(�o��)
�̂R�̋@�\���}�X�^�[����悢�̂ł���B���������a���x���@�i�`�s�l�j�̑�����C���[�W�����
�������₷���Ǝv���B��������ނ��������ނ̂�(input)�����A�����̑I����(process)�����A�o����
(output)�̕����ƂȂ�B
��L�����݂ɑ����悤�ɂȂ�܂Ŕ��N�����������A�I�����̍쐬�Ȃǒ��ёO�̏����ł���B
�Q���z���ŁA�}�X�^�[�ɒP����o�^���Ă����A�ɐ�����͂���A�ɋ��z�̌v�Z�y��
���̈���܂ŁA�ȒP�ɏo����悤�ɂȂ����B
���Ȃ�A���Z���ł��d�w�b�d�k���g���ĊȒP�ɏo���鎖���A���̓����͑�ςȘJ�͂�v���Ă����B
